蛍(ほたる)はむかし、自分と同じ名の虫にかどわかされそうになったことがある。
十年前の、蒸し暑い夏の夜。双子の弟の光(ひかり)と共に、蛍の多く棲む沢に出向いたのだ。母から禁じられていたのにもかかわらず。
いいこと、蛍、光。蛍の沢へ行ってはいけないよ。
もしかすると帰ってこれなくなるかもしれないから。
母はきつく言いふくめたのに、七歳のかれらは、幼さゆえの無謀な考えでひそかに家を抜けだした。
行きはよいよい、帰りはこわい。
沢の蛍は、小さな客人ふたりを歓迎した。尻の灯りをまたたかせ、舞い踊ってふたりの目を楽しませた。そのうちに夜はこわいくらいの速さで更けた。
行きは、よいよい。
沢のあたりには街灯ひとつない。急速に濃くなる闇にちっぽけな双子はいよいよ不安になって、蛍に告げた。あのう、ぼくたちもう帰ります。
帰りは、こわい。
蛍は無邪気に言った。さみしいことを言わないでおくれよ、まだいいじゃあないか、夜ははじまったばかりだよ。双子がいいえ帰りますと返しても、そうか、ひとの子は闇が怖いのだなと言うばかり。それならこれを飲んでごらん。沢の特別きれいな水と、山梨でつくったお酒だ。とても甘くておいしいよ。ひとくち飲めば、夜闇なんて怖くなくなる。と酒をすすめてきさえする。
酒は底まですきとおった透明で、一見水と変わりなかった。だがそれは闇の中ぼうと蛍の緑に光って双子の目をひきつけた。思わずふたりは見入ったが、はたと我に返ってやはり恐怖にみまわれた。
本能でわかったのだ。蛍は自分たちを帰さぬつもりなのだ、と。
母のことばがよみがえる。
もしかすると、帰ってこれなくなるかもしれないから。
ふたりは手に手をとって逃げだした。蛍は逃がすまいと追いかけてきた。道は純粋な夜色に閉ざされて、けれど妖艶な緑の光はあちこちに灯っていた。その光と光のあいだを縫い、引き裂くようにふたりは駆けた。足にまとわりつく蛍火はつめたくあつく、双子はぼろぼろに泣いていた。ただつないだ手だけがふたりの心を保っていた。
蛍と光がいないのに気づいた両親が探しにこなければ、ふたりはどうなっていたかわからない。
ふたりとも、なにひとつ知らなかったのだ。沢の蛍は神の眷属で、ひとならざるがゆえに無邪気だが残忍だということ。
それから。
それから。
もうすこしふたりが大きくなったら話そうと思っていたけれど、こんなことが起ったからには話さないわけにはいかないわ。
蛍、光。よくお聞き。
蛍はね、沢の神さまに愛された子なの。
それは蛍がなかばひとではないことを意味していた。神に愛された子はその愛に引きずられ、ひととしての存在が揺らぐ。
蛍という名も、同じ名にすれば蛍がかどわかそうとするのを止められると、母が考えたがゆえだった。もっとも、効果はあまりなかったけれど。
そんなことがあって以来、光は蛍という虫がだいきらいになった。無理もない。たいせつな兄を盗られそうになったのだから。
けれど当の本人、兄の蛍は暢気なものだった。
***
ことさら蒸し暑い夜だった。こんな夜、光は兄を盗られそうになったあの夜を思いだして不機嫌になる。もとより不快指数が高いのに厭な記憶が重なってはたまらない。
けれど蛍のほうは縁側にすわって、団扇で首すじをあおぎながらソーダ味のアイスキャンデーなぞを舐め舐め、上機嫌のようである。
蛍は近づいてきた光に気づいてほわりと笑った。そしてあろうことか、
「光、光。あのときの蛍は恐ろしいけれどきれいだったね」
だなんて言ってみせるものだから、光はその後頭部をおもいきりはたいてやった。
「阿呆。なに言ってやがる、あとちょっとで戻れなくなるところだったんだぞ」
蛍は涙目で後頭部をさすりながらも不満げに口をつきだした。光がもう一度腕をふりあげる仕草をすると、やっとその顔をひっこめた。
光はそのとなりに座りながら、あきれてため息をついた。
まったく、ひとの気も知らないで。
俺はいつもいつも、蛍のことが心配なのに。どこか遠くに行って、もう戻ってこないのじゃないかって。
蛍は神に愛された子だが光はちがう。この双子にそのちがいは、あまりにも残酷だった。
光は思っていた。
もし、ここじゃない、自分の知らないどこかに行くのだって、蛍と一緒なら怖くない。
だけど、俺は蛍とはちがう。
一緒に行くことはできない。
そのことを思うたび、もう小さな子どもでもないのに光はたまらなく泣きたくなる。だれかに、蛍に、抱きついておんおん泣いて行くな行くなと懇願したくなる。ほんとうのことを知って十年たった。されどその恐れは風化する気配すら見せず、むしろ年々膨張しながら光の心をむしばみつづけていた。
横目で蛍の顔をうかがうとやはりへらへらと笑っていた。むしょうに腹がたって、その手から溶けかけたアイスキャンデーを奪いとった。なにするんだよう、と子どもじみた声が上がったけれど意に介さず、光は水色の氷を歯で削った。すると一度に食べすぎたせいで頭がつきんと痛んで、また腹がたった。
光がひとり胃のむかつきと一時的な頭痛とたたかっていると、ふいに蛍が、あ、と声を上げた。光はびくりと身をふるわせた。蛍がこういう声を上げるとき。それは。
「光、水のにおいがする」
においがするほど近くに、沢はない。ましてや水のにおいなど、光には、すぐそばまで寄ってもかぎとることができるかさえあやしい。
あれ以来、蛍はときたま、こんなふうに光の知らない世界を見たり感じたりするようになった。
光にはそういうときがいっとう辛い。思い知らされるからだ。蛍と自分はちがう、ということを。
いっそ蛍を殺したら、こんなにびくびくせずにすむかな。
一瞬そんなことを考えてしまって、自分で自分がそらおそろしくなった。
と、ふいに、
「光、光」
同い年の弟の心うちなんてひとつも知らない、明るい声。その声と共に目の前につきだされたのは、光のそれとよく似た手のひら。
手をのばして、手のひらと手のひらを重ねる。重ねるだけで我慢がならず、つよくにぎりしめた。蛍はその力にいささかおどろいたようだが、うすく笑って握り返した。
そして光の鼻を、水のにおいがくすぐった。光の知らない、水のにおいが。それは湿っていてわずかに青くさく、吸っていると肺まで水が満たしていくような心地がした。
蛍の手は子どものものようにあたたかだった。
あの日も、この手だけがたよりだった。この手をはなさずいれば、蛍はどこにも行かずにいてくれるだろうか。
双子のかたわれの手を通じてにおう水のなか、自分がこの手で蛍をこの世界につなぎとめられたら、と光は痛いほど思った。
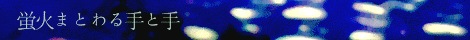
おしまい |