首長竜テノチティトランが旅に出た。よくあることだとせんぱいは言った。自分探しの旅ってやつ。心配しなくても、カサイ先生のところに人生相談に行くだけさ。
テノチティトランは美術部の家宝ならぬ『部宝』で、大理石の彫刻だ。体長は三十センチほど。表面はつるっとしていて、奇妙にあたたかみがある白をしている。
その、世界史の教科書からてきとうにつけたような名の彫刻が、いなくなった。ある放課後部活に来たらば、あるのは台座だけ。ご本人はこつぜんとすがたを消していた。
「すぐ戻ってくるさ。探しに行きたいなら行けばいいけど」
さがしにいかないのか、とあわてふためくわたしにせんぱいは言った。油絵を描く手は止めない。この余裕、これが年の功か。
カサイ先生とは、我が校の創立者、石持葛西の銅像だ。生徒玄関に鎮座して日々生徒を見守っている。そこに自分探しの首長竜が人生相談とは、どういうことだろう。
「そりゃ現代の恐竜ってのは、自分がわからない生き物だからさ」
「というと」
「たとえば皮膚の色とか。ティラノサウルス、何色か知ってるか」
「赤!」
「図鑑とかではだいたいそうだよな。でもそれ、うそっぱちだ。ほんとうはだれにもわかりゃしないんだ」
思わず首をかしげそうになったものの、考えてみればうなずける話だった。皮膚の化石に当時の色がのこっているはずもない。なにせとうのむかしに絶滅した生き物だ、わからないことは山のごとしだろう。
わたしが理解したのを見てとってか、せんぱいはまた手をうごかしはじめる。
「それよりな、ドドメ色マイスターキノサキ」
「なんだって」
「ドドメ色マイスターキノサキ。おまえ、パレット洗え」
せんぱいがちらりと視線をやったのは、放りだされた木製のパレット。わたしのだ。洗えと言われて当然。赤も緑も紫も黄色もみんななかよくまざりあって、そのどの色と言うこともできない混沌が広がっている。
どんなにきれいな色だって、吟味せずにすべてしぼりだせばしまいにああなる。
何色でもない、ドドメ色。なにもえらべなかった、なれのはて。
心のはしっこがしくりと鳴いたけれど気づかなかったふりをする。そんなことよりパレットを洗えというお達しのほうが問題だ。せんぱい、これは三ヶ月前から放置してあるんです。しかも油絵の具。
「これは宇宙を表現」「混沌だからって宇宙と結びつけるなおこがましい」
すげなくつっかえして、せんぱいはわたしにほほえむ。どこか脅迫的に、だ。
「城之崎ぃ、道具は大切にしろって、いつも言ってるよな」
う、とうめきがもれる。とはいえパレットのこの混沌模様……筆舌につくしがたし。逃げたい。逃げたいわたしの脳内にふとよぎったのは、カタカナのむれ。テノチティトラン。これだ。
「せんぱい、わたしやっぱり心配なのでテノチーを探してきます!」
とってつけたような物言いに、せんぱいはたちまちあきれかえった。わたしはみっともなく言いつのる。
「いつもはすぐ帰ってくるって言うけどそれは保証にならないし!」
引き止めてもむだだと思ってか、せんぱいは案外すんなり送りだしてくれた。
けれどきっと、逃げたのがわるかったのだ。きちんと尊敬すべき人生の先達の言にしたがっておけば、こんなことにはならなかったにちがいない。
カサイ先生のところに行くべく階段を下りるわたしのあたまのうえに、それはふってきた。
とっさに見上げたわたしの視界に一瞬で黒い幕が下りた。ぶつかる寸前の光景をわすれはしない。
階段の上から、首長竜がふってきて、わたしのあたまに直撃した。
なにせ大理石だ。おほしさまが、きらきらした。
◇
「よう子、まだか。ほかのみんなはもう決まったぞ」
おぼえてる、これはおじいちゃんが、孫をみんなつれてデパートにいったときのこと。なんでもすきなものを買ってやると言われた。
「ようちゃん、エビフライかハンバーグか決まった?」
これは小学生の選択給食のときのこと。クリスマスだけ、エビフライかハンバーグかすきなほうをえらべることになっていた。
「城之崎、志望校は決まったか」
これはつい最近のこと。中学三年生の、担任の声。
ようちゃん、よう子、城之崎。わたしの名を呼ぶ幾多の声。
そのさきにつづくのは、決まった? の催促。どれもが、隠しきれないいらだちをにじませている。いつだって最後の最後まで迷っているのはわたし。
なにもえらべない子どもだった。
「よう子の名前はね、太陽の陽と、太平洋の洋で迷って決められなかったから、ひらがななの」
名前の由来を聞く宿題。お母さんの声。
なにもえらべない子どもだ、いまも。でもしかたがないよねえ。優柔不断な名が体を表しちゃってるんだから。
視界をぬりつぶすのはドドメ色。何色ともつかない。どの色もえらべないから何色にもなれない。
◇
気はうしなわなかったものの、手すりにもたれかかったままうごけなかった。きのさき、と呼ばれて我にかえる。せんぱいの声だと思って顔を上げたらやっぱりせんぱいだった。
「せんぱい! 空から女の子が、じゃない首長竜が!」
「ここぞとばかりにそのセリフが出てくるなら、あたまは大丈夫だな。いや、むしろ大丈夫じゃないのか」
「たんこぶめちゃめちゃいたいです……」
痛みにみちびかれてそっとひたいに手をふれると、そこに小高い丘。熱をもっている。
「せんぱい、氷ー」
「はいはい保健室な」
あたりを見まわすと、そこは階段の踊り場だった。ちなみに十数段階段をのぼれば美術室だ。なんてこと、道なかばにして城之崎たおれる。
「おまえ、テノチーってさけんだろ。丸ぎこえだった」
せんぱいがわたしを助け起こしながら言った。うそだ、まったくおぼえがない。
と、立ち上がって気づいた。せんぱいが小脇になにかかかえている。見おぼえのあるシルエット。
「テノチー!」
またさけんでしまった。
せんぱいがかかえているのは、たしかに首長竜の彫刻だった。
ただ、違和感がある。なにかがちがう。
階段のくらがりのせいかと思った。けれど、それはたしかに、
「色、おかしくないですか」
「そうだな、城之崎、いやドドメ色マイスターキノサキ」
あろうことか、首長竜はドドメ色をしていた。つねの白色はどこにも見つからなかった。
保健室で氷をもらい、部室にもどりながら聞いたせんぱい仮説によると、テノチーがドドメ色になったのはわたしのせいらしい。反論する気はない。頭にぶつかる寸前に見た首長竜は白かった。だからぶつかったわたしのあたまのなかがドドメ色だったせいなのだ。
そんな女子高生いやだ。
「いやなのはおまえだけじゃないぞ、なあテノチー」
せんぱいが両手で首長竜を持ち上げる。テノチーは、首をだらんと下げてわたしと目をあわせようとしない。と思ったら、せんぱいにこたえてかなしげに鳴いた。
「ご、ごめん……。せんぱい、どうしたら元に戻るかな」
無情にもせんぱいは肩をすくめるだけだった。
「つめたい」
「そりゃあドドメ色マイスターキノサキ、先輩の言うことを無視して逃げた後輩に同情の余地があるか」
息がつまった。ごもっとも。保健室につれてきてくださったことだけでも感謝しないと。
せんぱいはひえびえと笑った。
「おまえのあたまのなかのせいでドドメ色になったんなら、ドドメ色を払拭してもう一回ぶつければ、ちがう色にはなるかもしれないな」
「それは痛いのでちょっと……。あ、そうだ! せんぱいの頭にぶつければべつの色に」
ことばは半ばで出てこなくなった。冗談じゃなく、せんぱいの目がぎらりと光った。ふざけんなってとこだろう、言いたいのは。
「とりあえずドドメ色のパレット洗え。形から入ってみ」
おとなしくうなずく。当然だ、そのことばから逃げてこうなっているんだから。
そして美術室にもどってきたら、お客さんがいた。
明治時代のひとだから、ちょんまげに和服。百八十センチの長身は、蛍光灯ににぶくかがやく。
石持葛西そのひとだった。もっとも銅像だけど。
いつも生徒玄関から動かないのに、どうしてここに。せんぱいと顔を見あわせていると、カサイ先生が口をひらく。りりしい顔の、ひきしまった口から発せられるのは、時代を感じさせるおもおもしい声、
「おじゃましてますぅ、テノチーに会いに来たんだけどいないから、ここにいればもどってくるかなって思ってェ」
ではなかった。男のひとが無理矢理たかい声をだしたときのひしゃげた音声が、美術室にひびきわたる。ごく端的に言うなればおかまさんだ。なんてこと、カサイ先生はおかまさんだったのだ……!
「城之崎。念のために言っておくけどな、史実の石持葛西はこうじゃなかったと思うぞ」
なんだ、そうか。銅像と本人はちがう。
それにしたって、銅像の顔は表情がほとんどうごかない。それでいて口から出てくるのが、
「テノチー!」
このあかるい声。外見と中身がへだたりすぎだ。
せんぱいの手の中の彫刻を見て、カサイ先生はおどろきの声を漏らした。
「まあひどい! それ、何色?」
テノチーだけじゃなく、わたしの心にまで会心の一撃だった。なにかするどいもので胸をつらぬかれ、地にぬいとめられたような心地がする。と思ったらほんとうにわたしは床にたおれれふしていた。氷のふくろが地に落ちる。
「いくら自分の色がわからないからって、やけになってそんな色になることないじゃない!」
「カサイ先生、こいつ今日も相談に行ってましたか」
「エエ。あいかわらず自分は何者かで悩んでて。今日はからだの色のこと気にしてた」
せんぱいのことばがよみがえる。恐竜は現代では自分がわからない生き物。そんな悩めるテノチーに、わたしはなんてことを! ほんとうの皮膚の色はだれも知らない。それをよりによって何色でもないドドメ色に染めあげてしまうなんて!
「わああああ、ごめんなさいいい」
「……。この子、どうしたの?」
「テノチーの色、たぶんこいつのせいなんです」
「うっうっ、ごめんなさい。わたしがドドメ色マイスターだから」
「おうい城之崎もどってこい。反省したのはよくわかった。おれは言いすぎた、すまん」
「だってわたしにはえらべないんだものっ、緑も黄色も紫もみんなすきだから、パレットに出しちゃうんだもの!」
「城之崎ー、泣かないでくれよ、すまんかった」
せんぱいがひざまづいて背中をさすってくれるのがわかる。けれど、せきをきったようにことばがあふれて歯どめがきかない。あたまをぶつけたときの白昼夢のこと。昔からなにもえらべない子どもで、周りをいらつかせてきたこと。みんな話していた。
「ごめんなさい、優柔不断でごめんなさいていうか生きててごめんなさい!」
視界のそとでせんぱいがおろおろしている。わたしの声だけが美術室にひびく。いけない、こんなことでまわりに迷惑かけてちゃいけないんだ。けれど、じわりじわりと涙はにじむ。
――よう子。ようちゃん、城之崎。
――まだ、決まらないの? また、えらべないの?
えらべないよ。
わたしには、なにも。
「キノサキちゃん」
さきほどまでより近くで、カサイ先生の声がした。
「泣くのはおよしなさいな。あのね、聞いて――」
涙と白昼夢の記憶でぐでぐでになった思考に、カサイ先生の声がさしこんでくる。
おかしなひしゃげた音なのに、その声色はひたすらにあたたかで。
どろどろをかきわけて、陽ざしのようにさした。
「なにもえらべないってことは、すべてえらんでるってことなのよ」
パラドックスにみちたことばに、ほうけて顔をあげた。
首が痛くなるくらい見上げないと、カサイ先生の顔は見えなかった。わたしの目の前に、なんとも頼もしい背の高い銅像が立っている。
先生、曰く。
「キノサキちゃんは、選択肢が目の前にひろがったとき、全部すてきだなって思って全部えらぼうとしてるのよ。だから決められないワケ」
ほんとうに、そうだろうか。
いや、そんなことない。そんなたいそうなこと、してない。だってわたしはたくさんのひとを不愉快にさせてきた。
顔色でわたしの心うちを見てとったのだろう。カサイ先生は、こう聞いた。
「じゃあアナタのすきな色って、なにかしら」
とっさに答えが出なかった。
問いの瞬間、思考が色の洪水であふれていた。
春の新芽のあわい黄緑。夏空に映えるサルスベリの上品なピンク。熟れた柿の橙。エメラルドを溶かしたメロンソーダの緑。真冬、白い世界にうかびあがるほほの赤さ。
どれがすきか、なんて。
そのどれもが、いとおしい。
「……ぜんぶ、かもしれない」
こう答えるしか、ないじゃないか。
つぶやくようなわたしの答えに、カサイ先生は勢いこむ。
「ね、すきだからえらべないの! それってちょっとステキじゃない? 世界を丸ごと愛してるみたいで!」
カサイ先生はあいかわらずの仏頂面なのに、前向きなことばには力があった。自分探しの首長竜が相談しにいきたくなるわけだ。涙が、いつしかひいている。
じっと見上げていると、カサイ先生がうなずいた。ぎぎ、ときしむ音さえしそうなぎこちない動作で。
「おれもそう思う」
ふいに横からせんぱいの声。視線があうと、せんぱいはちょっとてれくさそうにしながら、
「城之崎の絵は、どんな色も見捨てないなって。紫と黄色と緑とか、下手したら悪趣味な色づかいがきれいなんだ。それは城之崎が、ほんとにその色がすきだからだと思う。うん――」
それでもわたしを見て、わらった。
「おれは、城之崎の絵がすきだよ」
とくん、とくんと、胸のおくからひろがってくるなにかがある。ほんとうに。ほんとうに、わたしはわたしで。
なにもえらべないわたしで、いいの?
とまどいぎみにせんぱいを、カサイ先生を見る。せんぱいははにかむようにわらっている。カサイ先生は苦笑まじりに言う。
「テノチーにしろキノサキちゃんにしろ、悩みすぎ。何色でもないってのは何色でもあるってことよ? 夢があるじゃない」
ふいに言われて、テノチーがびくりと身をふるわせる。カサイ先生はふと思いついたようにあたりを見回して、それを見つけるとうっとり言った。
「ほらテノチー、見てごらんなさいよ、ステキじゃない」
ぎこちない動作で指さされたさき。そこにあったのは。
そこにあったのは、わたしの描いた油絵だった。
三ヶ月前、パレットをドドメ色にしながら描いた極彩色の花々。赤も緑も紫も黄色も青も、ピンクも水色も橙も、みんないとおしいからみんなえらんだ。
「何色でもないって、ああいうことよ」
小さな首長竜はじっとカサイ先生をながめていたけれど、やがてゆっくりとカンバスのまえに歩いていった。長い首をゆらりとたかくあげて、身のたけの数倍ある絵を見た。
ややあって、竜が一声鳴く。鼓膜をたしかにふるわせた、複雑なひびきのそれが、はじまりの合図だった。
色がはじけた。
テノチティトランの肌から、色がうきあがる。混ざりあってドドメ色だったそれは、もとの赤に橙に青に分かれて、宙にのぼる。カンバスの花とおなじ色が、わたしのいとおしい色たちが、宙に一瞬とどまってはふうわり消えた。湧きあがる色のむれは、首長竜をすっかりつつむ噴水。どこまでも、どこまでも広がっていく力を感じた。
ああ、ここにあったんだ。心うちで、ひとりごちる。
――よう子。ようちゃん。城之崎。
――まだ、決まらないの? また、えらべないの?
えらんだよ。えらんでいたんだよ。なにをえらぶか、答えはここにあったんだよ。……いつだって。ただ、わたしが気づかなかっただけで。
視界がすっとひらけた感覚が、ここちよい。
色の噴水はしだいにちいさくなり、やがてかききえた。
首長竜テノチティトランは、もとの白にもどっていた。
とん、と肩をせんぱいがたたく。
「よかったな」
「……う、うええ」
「は、泣くのかまた!?」
どうしてだか涙が出る。ぼろり、と涙の大きなつぶがこぼれてこぼれて、透明なしずくがつぎつぎ床に落ちる。
うれし泣きねえ、というカサイ先生の声が聞こえた。うれしいなんてものじゃなかった。でもそれをことばにすれば、たちまち陳腐になってしまう気がして、かろうじてこれだけ言った。
「ど、ドドメ色ばんざい……」
「……城之崎、パレットは洗えよ……」
首長竜は何色でもない。自分の色を探して旅に出る。
けれど探しものは、いつも旅人自身とともにある。
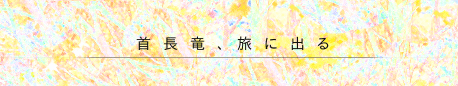
おしまい |